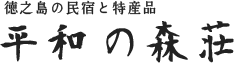- トップ
- 宿のご紹介
宿のご紹介
平和の森荘からのご挨拶
- 2015年(平成27年)に承継
- 民宿平和の森荘は徳田豊成が1981年(昭和56年)7月13日創業。
創業者の徳田豊成(令和元年没)が高齢になり、長男の徳田幸男が2015年(平成27年)に事業を承継。
父母の創業の志を承継しつつ、私たちなりのサービス提供を心がけてまいりますので、徳之島旅の宿としてご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
- 目指す宿像
- 昭和レトロな雰囲気が漂うアットホームな民宿です。
家族経営の小さな宿ですが、田舎の実家への里帰り感覚でご宿泊いただける宿になることを目指しています。
慌ただしい都会の喧騒を離れて、徳之島のゆったりした時間を存分にお楽しみください。
- 家庭的な宿
- 黒糖焼酎が大好きな経営者が皆さまの夕食の際に焼酎片手にお邪魔したり、遊びに来た近隣に住む孫たちがお騒がせすることもあるかもしれませんが、
民宿平和の森荘はそういう家庭的な宿だとご理解いただければ幸いに存じます。
- 施設について -
 建物は木造平屋のトタン屋根構造です。
建物は木造平屋のトタン屋根構造です。
すべて昭和の時代に大工気のある創業者が、知り合いの大工と一緒に手作りしたものです。
増築と結合を繰り返した結果、バリアフリーの構造にはなっておりません。
継承した際に一部を改装しましたが、ほとんどが元のままの状態です。
屋根が防音構造になっていないため、雨が降るとトタン屋根をたたく雨音が聞こえてきます。
敷地総面積は約1haあり、敷地内にはガジュマルの大木が特に夏場の涼を取る場所として大切にしています。
ハイビスカスやヤシ類・パパイヤやバナナなどの熱帯性植物などが植えられており、自由に観賞することができます。
また、ヤギの飼育もしていますので、是非触れ合っていただきたいと思います。
広い敷地全体をどのように活用するかを鋭意検討中です。
- お料理と特産品 -
- アクセス・周辺環境 -
 徳之島子宝空港のすぐ近くに位置し、イノー(内海)を挟んだ約400m西のリーフ上に滑走路の北端があり、日々航空機が離着陸しています。
徳之島子宝空港のすぐ近くに位置し、イノー(内海)を挟んだ約400m西のリーフ上に滑走路の北端があり、日々航空機が離着陸しています。
ご宿泊いただく9割強のお客様は空の便を活用していらっしゃいます。
徳之島子宝空港からは車で約5分。
Aラインとマリックスラインの運航する鹿児島・那覇航路の定期旅客船は毎日定期運航しており、
亀徳新港発着の下り便は9:10着・9:40発、
上り便は16:20着・17:00発となっています。
亀徳新港から徳之島子宝空港までの路線バス所要時間は約54分です。
Aライン系列の「奄美海運」が運航する“フェリーあまみ”は鹿児島・喜界・名瀬・古仁屋・平土野を結んでおり、
平土野港は12:20入港・12:50出航。
入出港は火・木・土の週3便。
同"フェリーきかい"は鹿児島・喜界・名瀬・古仁屋・平土野・知名を結んでおり、
平土野港は12:20入港・12:40出航ですが、上り便は平土野港には入港しませんのでご注意ください。
入出港は水・金の週2便。平土野港までは車で約10分。
<駐車場>
敷地内には十分な駐車スペースがございますので、予約なしでも対応可能です。
<送迎車両>
10人乗りのハイエース1台を所有していますので、事前にご連絡いただければ徳之島子宝空港・平土野港までお迎えに上がりますし、送りも対応可能です。
亀徳新港発着のお客様につきましては、徳之島子宝空港まで路線バスで移動していただき、空港バス停まで送迎させていただいております。 海抜は約4mで西の境界は防波堤となっており、リーフ上の徳之島子宝空港滑走路の間には広大なイノー(内海)が広がっています。
海抜は約4mで西の境界は防波堤となっており、リーフ上の徳之島子宝空港滑走路の間には広大なイノー(内海)が広がっています。
鹿児島空港や奄美空港・沖永良部経由で那覇空港を結ぶJAL便は、目の前の徳之島子宝空子を離発着するのを見ることができます。
潮の干満によっていろいろな表情を見せてくれるイノーは、満潮時でも浅いため海水浴には適しませんが、潮が引く白い砂浜が広がり、手軽に散策することができます。
天気と潮目の良い日の夜には、イザリ漁(漁火漁)の明かりを見ることができます。
漁ではノコギリガザミやイシュタナガ(アマエビ)などが獲れますし、
リーフの沖側ではタコやイセエビ・ブダイなどの漁場です。
2月中旬から5月上旬まで、イノーの岩場は天然のアオサ(ヒトエグサ)で緑に染まり、アオサ摘みの多くの皆さまが繰り出します。
天気のいい日の夕刻には、東シナ海の大海原に沈んでいく夕日を眺めながら、しばし心静かにお過ごしいただけます。
民宿の敷地の一角からは、徳之島の代表的な景観「寝姿山」も木々の間から見ることができます。
「平和の森荘」 屋号の由来
 「平和の森」とは「平和の森」とは、すぐ近くのモクマオウ林に由来するものです。
「平和の森」とは「平和の森」とは、すぐ近くのモクマオウ林に由来するものです。
先の第二次世界大戦末期の陸軍特攻隊中継基地「旧陸軍浅間飛行場」は、民宿から南へ約1km。
鹿児島の知覧や万世から特攻隊として多くの若者たちが南方に向け出撃していき、沖縄の空で散華しました。
戦後間もなく、飛行場跡地最北端の広大な砂浜にモクマオウ林を造林。
1975年(昭和50年)6月には、特攻隊として戦火に散った若者の御霊を慰めるために「特攻平和慰霊碑」が建立されました。
碑は旧滑走路の北端のモクマオウ林を背景に南向きに建てられています。
この慰霊碑の建立を機にモクマオウ林を「平和の森」と称するようになりました。
ところが、2019年にモクマオウ林を所有する浅間集落が全ての木を伐採してしまったため、現在は広々とした空間が広がっています。
| 『創業の決意』 | 1981年(昭和56年)、創業者の徳田豊成が農業に手詰まり感を持ち、小さな民宿を開業することを決意。 |
|---|---|
| 『事業着手』 | 当時、天城町松原ですでに民宿として開業していた「宮田荘」と、徳之島町下久志の「ときわや」を視察。 大工気のある創業者は早速、自分で図面を引き基礎工事の準備に着手。 その間に知り合いの大工数人に声をかけて木材等の材料を搬入して加工を始めた。 作業を進める中で、トイレの設置や調理室・食堂の確保などで面積が少しずつ膨らんでいったが、農地を処分するなどして資金を調達。 約3か月でお客様を受け入れる環境が出来上がりました。 |
| 『完成のお披露目の席』 | 徳之島では家屋を新築しますと、親族や集落の皆さま・知人友人を招いてお披露目の祝いをする習慣があり、早速皆さんを案内して新築祝いと相成りました。 その席でお祝いの言葉等をいただきましたが、まだ正式な屋号を決めていなかったため、とりあえずは「徳田荘」ということでその場を進めることとなりました。 宴が進むにつれ、出席の皆様からいろんな意見が出されました。 創業者から、「多くの皆さまにご利用いただく施設にするためには、皆さまのご意見を参考にしたい。」との言葉があり、 すぐに紙片を準備して出席者の皆さまに配って、その場で思いつく屋号名案を記載してもらい回収させていただきました。 |
| 『屋号の決定』 | 翌日、皆さまの提案を整理したところ、最も多かった「平和の森荘」に決定。 冠を「旅館」とするか「民宿」とするかについては家族で話し合った結果、創業者の強い意向を反映して「民宿」とし、旅館業営業許可の施設の名称は「民宿平和の森荘」となりました。 (営業許可:昭和56年7月13日付) |
敷地内の動植物
【動物】

ヤギ
| ヤギ | 民宿の敷地の一角に飼育しているヤギ。 一時期飼育を中断しておりましたが再開しました。 人見知りの子たちですが、お泊りの際にはぜひ覗いてみてください。 |
|---|---|
| ニワトリ | 南アメリカのチリ原産アローカナ種のニワトリ飼育を始めました。 青い卵を産みます。 飼料はJAから仕入れる配合飼料とトウモロコシ・残飯を与えています。 ご宿泊いただくお客様に召し上がって頂けるよう増やしているところです。 |
【植物】

ハイビスカス
| ハイビスカス | ハイビスカスは葵(あおい)科の植物。 インド洋や太平洋の島々が原産地で、ハワイに持ち込まれてから広まったとされる、ハワイ州の州花。 学名は「ヒビスカス」ですが「ハイビスカス」と呼ばれており、別名「仏桑花(ぶっそうげ)」とも言います。 マレーシア・スーダンの国花。いかにも南国の花という感じのくっきりした赤色が印象的な花ですが、黄色やピンク・だいだい色の花もあります。 沖縄では、花びらをハイビスカスティーとして飲用しているようです。 7月11日・9月22日の誕生花で、花言葉は「勇ましさ」「華やか」です。 挿し木で簡単に増やすことができ、夏の乾燥にも強く、土壌も選ばないため、もう少し街路樹としての活用を検討する必要を感じます。 温暖な徳之島では一年中花が咲いて私たちの目を楽しませてくれる貴重な花といえます。 民宿の敷地内では数種類のハイビスカスの花を一年を通してご覧いただけます。 現在、民宿の玄関脇に植えてあるハイビスカスと、花鉢に植えたハイビスカスが鮮やかな色彩でお客様をお迎えしています。 |
|---|---|
| ブーゲンビリア | ブーゲンビレアは白粉花(おしろいばな)科の植物で、「ブーゲンビリア」と呼ばれることが多いです。 フランスの科学者で探検家の「ルイ・アントワーヌ・ブーガンヴィル」さんがこの花を最初に発見したことから、その名前にちなんで冠されたとのこと。 別名「筏葛(いかだかずら)」とも言い、原産地は南アフリカ地方。 代表的な熱帯花木で徳之島では一年を通して花を咲かせます。 色づいた花びらに見える部分は花を取り巻く葉(包葉)であり、通常3枚もしくは6枚あります。 7月20日の誕生花で、花言葉は「あなたは魅力に満ちている」です。 挿し木で簡単に増やすことができ、現在鉢植えによる栽培を試験中ですが、強剪定をすることで花を咲かせることができるようになりました。 今後は剪定から花を咲かすまでの期間を調節できないか試していく予定です。 |
| クロトン | クロトンはマレー諸島からオーストラリア、太平洋諸島の熱帯地域に広く分布する、常緑の低木です。 自生地では生垣として利用されるほか、育てやすいことから観葉植物としても古くから親しまれています。 日本へは江戸時代末期に伝わり、明治時代の終わりから本格的に栽培されるようになりました。 草丈は10~150cmと品種によって様々で、白・赤・紫・黄色といった様々色の葉っぱをもっています。 突然変異しやすく、今では100を超える園芸用の品種があることが、「変葉木」という別名の由来です。 また、7~8月頃になると、白や黄色の小さな花を咲かせます。 ただ、小さく目立たない花なので、よく観察して見つけてくださいね。 色とりどりの葉の色を楽しむことのできるクロトンの鮮やかな色彩は南国ならではです。 |
| ユリの花(ユイヌハナ) | 敷地内で自然に増殖していくユリは、4月から6月上旬まで花を咲かせます。 |
| ツツジの花 | 在来のツツジと園芸品種のツツジがあり、4月いっぱいが花の見頃です。 |
| ソテツ(方言名:シティーチ) | 乾燥に強いソテツは夏場でも濃い緑の葉を維持します。 5月に入ると雄花と雌花が咲いて、受粉を手助けすることで10月ごろにはたくさんの赤い実をつけます。 現在でも味噌の材料として重宝しています。 |
| アダンの木(方言名:アダーネィ) | もともと海岸地域に自生するアダンの木。 雌雄別株があり、雌の木にはパイナップルのような実がなり、7月下旬ごろから次々と色づいて甘い香りを漂わせます。 熟して落下した実はオカヤドカリの絶好のえさとなります。 ごつごつとした外側の種は、いったん乾燥した後に一斉に発芽します。 |
| ビローの木(方言名:クバ) | 南国を代表する植物のひとつです。 在来のビローの木を数本移植したものが実をつけて増殖しています。 |
| ココヤシの木 | 徳之島には自生しませんが、漂着したヤシの実が発芽しているのを海岸で拾ってきて植えました。 かなり大きくなって実をつけ始めています。 タイワンカブトに気をつけないと幼虫に成長点を食害されて枯れてしまうので、年に数回薬剤を散布しています。 |
| ガジュマル(方言名:チンバ)の大木 | 大きな木陰を作っていて、夏場には涼を取る場所として、また集いの場所として重宝されている空間になっています。 |
| パパイヤの木 | 徳之島ではパパイヤはフルーツとして食べることはほとんどなく、野菜として使っています。 |
| シャカトウの木 | 夏場に実がなりますが、ごわごわした表皮が御釈迦様の頭の様子と似ていることから「シャカトウ」と呼ばれているようです。 とても甘いのですが、ほとんどの部位が種で食べるところは少ししかありません。 日持ちしないのが悩みです。 |
| イエローストロベリーグァバ | 小ぶりですが甘さ抜群のグァバです。 繁殖力が強く、敷地内にどんどん増殖してしまうのが悩みです。 |
| ヤマモモの木 | 在来種のヤマモモと、大粒の瑞光を植えてあります。 6月下旬ころから色づいて食べることができます。 |